本文
一駅一事業石神前駅編を作成しました
石神前駅編
石神前駅周辺のおすすめスポットについて、無人駅マイスターに聞いてきました!
石神前駅とは
二俣尾一丁目にある石神前駅は、1928年に青梅鉄道の駅として開業されたが、名称は現在と異なっていました。
1921年に青梅鉄道が経営する遊園地(楽々園)が開園しており、最寄り駅として誕生した当時は、楽々園停留場という名称でした。
1929年に青梅電気鉄道に社名が変更になっても、駅名は変わりませんでしたが、1944年に青梅電気鉄道が国有化された際に三田村駅に駅名が変更され、さらに3年後の1947年に現在の石神前駅に名称変更されました。

石神前駅マイスターの渡邊さんにインタビュー!
石神前駅の魅力や周辺のおすすめスポットについてインタビューしてきました!
・無人駅マイスターさん紹介
石神前駅の駅マイスターを担当しているのは、渡邊真由さん。
東京アドベンチャーライン内の無人駅11駅に
それぞれ存在する駅マイスターのリーダーも務めています!
無人駅マイステーション化プロジェクト・駅マイスターとは?
東京アドベンチャーライン内には、無人駅が11駅あります。そのすべてを青梅駅が管理し、月1~2回程度の巡回清掃などを実施していました。もっとひとつずつの駅に特化した管理体制はできないかと思案し、有人駅と同様のサービス環境を保つために発足したのが、無人駅マイステーション化プロジェクトです。
「お客さまにとって無人駅でも有人駅でも駅には変わりはない」の想いのもと、11駅に「無人駅マイスター」を定め、責任と誇りをもって管理しているそうです。

石神前駅の観光スポットを巡るモデルコース
石神前駅から二俣尾駅に向かう、モデルコースを紹介します。
総距離数:3.7km 所要時間:約1時間 ※各施設の滞在時間や休憩時間を除く
(1)石神前駅→(2)石神社→(3)ブリヂストン奥多摩園→(4)好文橋→(5)一の滝→(6)即清寺→(7)青梅市吉川英治記念館→(8)愛宕神社→(9)海禅寺→(10)二俣尾駅
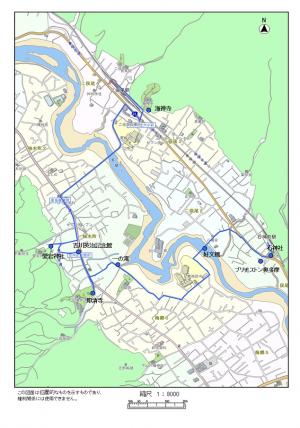
石神前駅<外部リンク>
現在の石神前駅の名前が示すとおり、石神社の最寄り駅になっています。駅のシンボルマークには、石神社の境内にある、幹周6.5m、樹高25m を超える市指定天然記念の巨大な イチョウの樹が描かれています。

石神社<外部リンク>
祭神は磐長比売命(いわながひめのみこと)。創建は不明で、古くは石神大明神と称されていました。明治6年に村社に列格。
『武蔵名勝図会』によると、「土人いう、当社は石神(いそのかみ)明神と称したが、誤って上(かみ)を神としてしてしまった。本来は奈良県の石上神宮を勧請したもの」といわれています。「御神体は丸き石なりとも云う」ともあります。
別当は青梅山金剛寺で、末寺の泉蔵院と正明院が隔年交代で奉仕したといわれています。
境内のイチョウの木は、市の天然記念物に指定されており、紅葉の時期には鮮やかに色づきます。
-石神社と大イチョウ-
ブリヂストン奥多摩<外部リンク>(旧楽々園)
石神前駅誕生のきっかけとなった旧楽々園。跡地にはブリヂストン奥多摩園があります。
株式会社ブリヂストンの保養地ですが、庭園は有料で一般の人にも公開されています。
庭園内では四季折々の自然を体感できますが、特に秋は見事な紅葉を楽しむことができます。
※場合によって観覧不可となる日もございます。
観覧ご希望の際は、公開日や料金の詳細について、
必ず事前にブリヂストン奥多摩園にご確認ください。
-ブリヂストン奥多摩の紅葉の様子-
-入り口にはブリヂストン奥多摩園の看板-
好文橋<外部リンク>
二俣尾地域と梅郷地域を結ぶ人道橋です。
季節に応じて、新緑や紅葉を楽しむことができます。
-好文橋から見た多摩川-
一の滝<外部リンク>
滝を見るために近くへ行けるよう、2022年に整備されたばかりの観光スポットです。
青龍の滝の別名もあります。
即清寺<外部リンク>
真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)の寺院です。
元慶年間(877~884年)元喩和尚の開創、建久年間(1190~1198年)に源頼朝が
畠山重忠に命じて造営、印融和尚が中興したそうです。
三田氏を滅ぼした後北条氏に仕える北条氏照にも信仰されたほか、
慶安元年(1648年)には、徳川氏から明王堂領三石の朱印状を寄せられた。
青梅市吉川英治記念館<外部リンク>
吉川英治は『宮本武蔵』など数多くの名作を生み出した昭和の代表的な国民文学作家で、今なお多くの人々に親しまれています。
青梅市吉川英治記念館(草思堂)は、吉川英治が昭和19年から同28年までの約9年間家族と共に暮らしていました。

愛宕神社<外部リンク>
祭神は火産霊神(ほむすびのかみ)で、御神体は本地勝軍地蔵です。
創建は伝えによると、元慶年中(877~884年)で、即清寺の開基にともない、
その守護のために創建されたといわれます。その後、建久年中(1190~1198年)に、
源頼朝が畠山重忠に命じて、山頂に社殿を再建したともいわれています。
また、『皇国地史』によると、三田弾正の祖先で相馬師門の後裔師秀が辛垣城築城の際に、
その鎮護のため愛宕神社を勧請したのであろう、ともいわれています。
-愛宕神社の急な石段-
-春には石段周りのつつじが美しく咲きます-

海禅寺<外部リンク>
1460~66年に開山。この地方の豪族、三田氏の厚い保護を受けたが、1561年辛垣城陥落の際の兵火で焼失したと伝えられています。その後、焼失と再建を繰り返し、現在、境内地は東京都指定史跡になっています。本堂の左手には、三田氏の供養塔である4基の宝篋印塔が11基の五輪塔と共に並んでいます。前庭には、市指定天然記念物の市内最大級のクスノキ3本があります。

参考文献
参考文献
『おうめ文化財さんぽ』(2019)
『青梅を歩く本』 (1994)
『青梅歴史物語』(1991)
『青梅市史 (上巻)』(1995)
『青梅市史 (下巻)』(1995)









